2005年1月の日記
淀川長治が、『プライベート・ライアン(以下SPR)』をプライヴェートな物語と評する際、彼はプライヴェートとパブリックの動的な相互関係について言及している、と見ることもできるだろう。
『SPR』で語られるのは、生き残ってしまった老人の負い目が形成されるまでの過程であり、それは劇中で、ミラー大尉側、ライアン一等兵側の両者から投じられる疑問に要約される。ミッションに対して費やさねばならぬ犠牲が大きすぎるように思われてしまう。
けっきょく、ライアン一等兵のために、ハンクス軍団はほぼ全滅してしまい、彼はミラー大尉の墓前で頭を抱えてしまう。ところが、その不釣り合いに対する解答はすでに与えられていて、振り返ると絶滅したハンクス軍団に相当する彼の子や孫が立っている。
ライアン一等兵の負い目は、ごく個人的な負い目であると同時に、ハンクス軍団はGI(政府支給品)であるため、それは共同体への負い目でもある。その負い目が、時間と血縁を越えたところで報われるに及んで、わたしどもは、個人的な義理とか人情の背後にある、公共とも言うべき空間の広がりを見ていることになる。
実際の問題として、よほどの想像力がないと、何か抽象的なものに多大な犠牲を払うのは難しい。ゆえに、その善悪は置いておくとして、共同体の正統化を行う言説において、ただ、その共同体のために殉じろとだけ要請するのは、適切な戦略とは思われない。普通に市民生活を送る上では、共同体という言葉が抽象的すぎてピンとこない。したがって、共同体を実感せしめる戦略が必要になってくる。
例えば、その抽象物は、あくまでプライヴェートという顔の見える物語の中で語られねばならない。公共という神話を語るために、わたしどもは私の物語を語らねばならない。『SPR』で、共同体という抽象物が、個人的な負い目のなかに実体を得るように。そして、共同体を語る私の物語は、近代小説の体裁と近似することになるだろう。それは、ただ特殊な個物を通してのみ普遍的なものが象徴されると見なすような世界(柄谷[2001:536])だから。
柄谷行人 2001 『増補漱石論集成』, 平凡社
志賀直哉『暗夜行路』
『暗夜行路』は、謙作の片務的な視野の中で、その多くが語られている。そこにあって、彼はたいへんなる頻度で女性に欲情し、錯乱し、わたしどもを驚き呆れさせる。ただし、あくまで頻度の問題であって、特定の女性に投じられるパッションそのものは、特に逸脱的ではない。恋愛を見出す感受性の方が肥大してる。
謙作の度重なるラブ・アット・サイトを可能にしたのは、即物的に考えてしまえば、金と時間の保証による思考の奇態化と思われる。これは、多くの場合、不安とか焦燥に至るものだが、謙作のケースにおいては、恋愛の感受性の肥大につながったといえるだろう。そして、彼の感受性が問題とされる限り、恋愛の契機には、外因的と言うよりも内因的な色彩が濃くなる。彼は娘どものハーレムに放り込まれたのではなく、むしろ世界の中にハーレムを見出している。
もっとも、お話が謙作の視角で語られる以上、それを通して世界を眺めるわたしどもにとっても、ハーレムが内在しようと外在しようと結果は同じで、ただ、世界は、萌え萌な人格が逐次的に投入されるような形で顕れてくる。すなわち、幼なじみ→メイドさん→妹→病人。
彼が本統に愛子を可憐に思い出したのは彼女が十五、六の時に彼女の父が死んで、その葬式に白無垢を着て、泣いている姿を見た時からであった。
(岩波文庫版・前編67頁)
幼なじみ萌えは、ごく標準的な人格の立体構造化によって始まっている。愛子は五つ年下で、子どもの頃の謙作は彼女を五月蠅げ思う。それで歳月は流れ、上記の如く幼なじみ化してしまい、女学校での試験勉強を手伝ったりしてはドキドキ。たいへん腹立たしい。しかし、大人の事情でこの恋愛は実らない。
彼はいても起ってもいられない気持ちで、万一の空想に胸を轟かせながら、階下へ下りて行く。お栄の寝ている部屋の前を通って便所へ行く。彼の空想では前を通る時に不意に襖が開く。黙って彼はその暗い部屋に連れ込まれる。――が、実際は何事も起こらない。彼は腹立たしいような落ち着かないような気持ちになって二階へ還って来る。
(前編136頁)
このメイドさんは、かなり誇張して描画すると、
「朝帰りなんていけません。何の連絡もよこさないで、一晩中心配してたんですよ」
「ボクはもう大人なんだい。朝帰りくらいするんだ」
「ダメです。罰としてキスしちゃいます」
「ほええ」
な感じの人で、『水月』の雪さんを常識的にしたようなメイドさんである。引用した如く、ただでさえ猛りがちな謙作の妄執は、播磨で暇を持て余した折りに制御が効かなくなり、ついには彼女への求婚に及んでしまう。メイド萌えにとって、それは致命的なイヴェントといわざるをえない。実際に婚姻が成立しようとしまいと、求愛が行われた時点で、彼女の人格からメイド性が剥奪されてしまい、ご主人様とメイドさんの関係が終わってしまう。
妙子は想わせぶりな顔つきをしながら、
「これは謙様の……」といった。「今お開けになっちゃ、いけない事よ、京都へお帰りになってから見て頂戴」
「どら、ちょっと見せろ」
「いやよ」
「お祝いか?」
「いい事よ、お兄さまには関係のない事よ。黙っていらっしゃい」
(後編91-92頁)
謙作には妹が二人もいて、狂人に刃物とも称すべき事態といえる。上記の例は、奈良で娘に欲情し、親戚総動員でスケコマシ攻勢を図った結果、結婚に持ち込んだ兄を祝福する妹の図で、「てよだわ」言葉の破壊力が清々しい。
おそろしいことに、以上は氷山の一角にすぎず、他にも謙作は風俗嬢に熱を上げたり、電車で乗り合わせた子連れの人妻に忘我したり、ウェイトレスさんを口説き始めたりと、閑人の肥大を語るに枚挙の暇がない。しかし、後編に至り、新婚生活ののろけ描写が始まると、さすがに頻発性の欲情は抑止されてくる。あるいは、分散していた情欲が、ひとりの女性へ集中運用されるようになる。その結果として投じられるのが、冒頭の終わりに挙げた病人萌えで、これは他の萌え人格と違い、罹患してしまうのは謙作自身であり、奥さんの方が彼に萌え萌えしてしまう。つまり、それまで謙作の内語で扱われてきた世界が、ここで別の人格の視覚の中に移行してしまう。それは、病という有効な感情導入イヴェントが、その対象に関して無差別的であることを、よく表してるエピソードと思う。周知の通り、娘は往々にして罹患する生き物であるが、反対に、主人公男が罹病して、娘による看病シークエンスが始まることも度々である。
病気萌えの無差別性は、より普遍的に考えると、恋愛の力関係に関する萌えの両義的な側面を示唆してる。罹患したわたしどもは、娘の保護下にあるので、主導権は娘にあるように思われる。ところが、娘の方は罹患したわたしどもに心配でドキドキしている訳で、その意味で主導権はわたしどもの方にも存する。これは、誰かに惚れて意識の過剰を起こす娘一般についてもいえることで、主導権は娘を発狂させた人間にあり、同時に、その娘の狂態がわたしどもの思考の枠組みを破壊してしまうという点で、娘自身にもある。
『暗夜行路』の場合、この両義性によって、統一した人格の内語で語るという物語のイマジナリーラインが越えられてしまった、と考えることもできるだろう。
グレッグ・イーガン『宇宙消失』(1)
ある部族で青年が成人するにはライオン狩りでその力を証明せねばならないので、狩り場に二日かけて行き、狩りの後二日かけてもどる。酋長は彼らの成功を祈ってその間踊り続けるが、問題は、狩りが終わった日から青年たちが帰路にある間も踊り続けるというのである。そのとき狩りはすでに終わって事の正否は定まってるのに、その幸運を祈るのはどうしてだ(大森[1996:70])。
例えば、冷蔵庫の食料を切らした螢一が餓死の危機に陥った際に、ベルダンディーのとった行動を考えてみよう(『ああっ女神さまっ』)。彼女は、食糧が供給されるよう祈念する。その祈願の真っ最中にやって来るのが、北海道から上京してきた恵で、彼女はダンボール数箱分に及ぶ食料品をともなっている。
ここで問題としたいのは、常識的な時系列の感覚から女神の法術が逸脱している点である。ベルダンディーがそれを用いるずっと以前から、恵の東京行きは決まっていたと思われるし、少なくとも前日には、北海道の実家を立っている。つまり、法術が実効する以前から、その法術を達成すべく行動が始まっている。これは如何様に考えればよいのか。
冒頭に挙げたマイケル・ダメットの問いにもどってみよう。
過去が過去として認知されるには、ある種の制度的な条件をクリアせねばならない、とする考え方がある。刑事事件は司法捜査の手続きを経ないと公式の過去として見なされないし、自然法則にしても例外ではない。見方を変えれば、そうした手続きがなされるまで、過去は過去として存在していない。よって、大森[1996:74]によれば、すでに過去となってるライオン狩りは、真理条件をパスしないうちは、公認の過去とはなっておらず、酋長は、ライオン狩りの成功が制度的要件を達成するように祈っているわけである。
過去が一定の手続きを経て、初めてわたしどもの前にあらわれてくる景観は、女神さまの法術を解釈する上で、ひとつのヒントとすることもできる。すなわち、あの法術は過去という不確かなイベントを実存せる現象に還元するメカニズムそのものではないか。
もちろん、この理屈には間隙がある。過去認定の手続きそのものが、手続きの対象となったイベント自体に物理的な現象を及ぼすはずがない。しかし、もし及ぼすとしたらどうだろうか。そこに、グレッグ・イーガンの如何にもファンタジーな飛躍があって、彼の言葉を借りるなら、シュレディンガーの猫は、観察者の到来する以前は死んでもいないし、生きてもいない。生と死が混合された状態にある。けれども、わたしどもは、そんな状態にある猫を想像することはできない。それは、にんげんが観察しうるものを知らぬ内に片っ端からひとつの可能性へ収縮させてしまう生き物だからだ。そして、その収縮に恣意性が持ち込まれ、望ましい固有状態の制御に至ると、女神さまの法術が見えてくる。
それは、目眩すら覚えてしまうご都合主義というべきもので、女神さまの法術で、本来なされるべき収縮が阻害された結果、さまざまな可能性上の恵が併走する。北海道特産品を携えない恵もいるかも知れないし、そもそも上京を決断しない恵もいるかも知れない。そうした、何億もの恵の中から、今、この時間、この場所に北海道特産品を持参する恵へ可能性が収縮する。
それでは、収縮の自在な状況にあって、過去は如何なる意味合いを持つのだろうか。そもそも、過去というイベントそのものがあり得るのだろうか? この辺から、グレッグ・イーガンの問いかけが始まることになる。また、女神さまがこの種の心的混乱を回避し得てるのは、彼女たちに課せられる厳しい条件付けあってのことと解することもできるだろう。
大森荘蔵 1996 『時は流れず』青土社


換気扇口の猫。
俊英演出家のI氏は、福岡の生まれである。氏は、たいへんナイーヴな人で、私どもが九州人に抱きがちな豪放なイメージ、例えば、猛勇の過剰を持て余し、何も考えず戦線を突出させてしまった結果、後方の師団司令部を襲撃されてしまった大陸の熊本第六師団の如くな蛮性――を普段は微塵も匂わせない人であり、ステレオタイプが如何に当てならないか、私どもに教えてくれる。しかしながら、氏もやはり九州人のはしくれには違いなく、その厳重に隠匿された本性は、酒の席でしばしば開花し、私どもを恐怖のどん底に突き落としてしまう。氏は酒乱であった。外受けの某作品の打ち上げ会場では、キャラデザの某巨匠アニメーターの下の名前を連呼して罵倒。当人は目の前である。また、会社の忘年会の席上、社内の大御所アニメーターの一々を挙げて、聞くも恐ろしい辛辣極まる論評に耽り、ついでに当人を目前にして某大プロデューサーを罵倒。あげくには、氏の師匠筋にあたる巨匠A監督にからみ始め、氏の隣にいた私などは、もう恐ろしくて恐ろしくて、酒に酔うどころの話ではなかった。
とにかく、三十を超えた立派な大人の飲み方ではない。大人というものは、酒に酔っても自分を売らないし、他人も売らない。しかし、I氏には遠く及ばないとはいえ、酒乱は当方にとっても決して他人事ではない。社内に親しい人も居ない私は、会社の隅でコソコソと独りで仕事をし、誰も気づかぬ内に帰宅するような、慎ましやかで内気な愛らしい人間であるが、酒の席となると、ついつい嬉しくなってしまい、陽気になってしまい、乱れてしまう。未だ、二十代の爽やかな青年っぷりを謳歌してるといえども、三十代の足音が次第に近づいてくる昨今、そろそろ大人の飲み方をせねばなるまいとは自覚するところである。けれども、泥酔し、自分を虐げて人の笑いをとるあの快楽が忘れられず、目も当てられない顛末に至る。しかも、I氏もそうらしいが、乱れるほどの痛飲も、決して当人の記憶は収奪してくれず、結果、昨日の言動が一字一句、克明によみがえり、莫大な後悔に身を持て余す朝となる。
その点では、制作のO氏や撮影のN氏が羨ましくも思えてくる。O氏もN氏も、I氏に負けないくらい恐ろしく乱れる人々で、酔ったO氏などは、色白で端正に生まれついた私にひどく嫉妬を催し、「おまえは結婚できない、結婚できない」とからんでくる始末である。N氏に至っては、泥酔のまま会社にもどり、一晩中床に転がりながら不明瞭な大音声を発し、徹夜仕事で会社に残る私の肝を大いに冷却せしめた。ところが、なんと幸福のことか、彼らはその一切を何も覚えていないのである。
もちろん、本当にどちらが幸福か、という問題は難しい。むしろ、どちらも不幸だというのが適切だろう。ただ、記憶の有無にもかかわらず、乱脈は歴然と存在することには変わりが無い。そう考えると、より苦痛のない戦略の方がマシなような気がしてくる。いわば、阿波踊り的な自棄糞ともいうべきで、つまり、同じ酒乱なら、忘却せねば損なのではなかろうか。
こうの史代『夕凪の街』
主にヴェトナム帰りという現象を語ってきた帰還兵というモチーフが、PTSDというタームによって普遍化されることによって、わたしどもは殊更に人をヴェトナムに放り込んで、酷い目に遭わせて、故郷に帰さなくとも、それと似たような心理を語れるようになった(間延びする戦場のトラウマ)。例えば、『パトレイバー2』と『カウボーイビバップ』はサイエンス・フィクションという枠組みで帰還兵を語り、『忘れられぬ人々』は任侠物の枠組みにその概念を取り込んだ。
『夕凪の街』の描画するイベント自体は、中沢啓治をはじめとする数々の言説の中で語られてきたものである。ただ、そのイベントを眺めるパースペクティヴが従来のそれとは異質で、いわば、これは、帰還兵という枠組みで戦術核の被災経験を語ってしまえることを発見してしまったお話といってよい。
中沢啓治とこうの史代の視角を区別しているものは、戦場からの距離感だろう。戦場から隔たった空間に至らないと、そもそも帰還という概念は成り立たたず、また、しばしばそこで語られる、生き残ってしまったことへの後ろめたい感傷が生まれない。

中沢の眺める景色は、時には喜劇として扱われるように、どんなに戦場から遠ざかった些細な日常も、あの呪わしき絵柄によって、戦域と化してしまう。常在戦場ならば、生き残ってしまったという自覚を抱くのは困難で、したがって、帰還兵というパースペクティヴで世界を語る発想がそもそも出てこない。対して、こうのの眺める景観は、そこでどんなにイベントが未だ継続中の事態であると強調されても、あるいは強調されるからこそ、事はすでに終わってしまっている。彼女の眺めるパースペクティヴ自体が、その終結をもって初めて可能になる類のものだから。
ところで、帰還兵もので語られる帰るという言葉には、ふたつの意味合いがあるように思う。それは、日常に戻ることであり、かつ、ふたたび戦場に戻ることでもある。物語が、生存への後ろめたい感傷の処理に失敗してしまうと、けっきょく、帰還兵は死に場所探しをせねばならず、それは戦場への帰還という形になりがちだ。『ディア・ハンター』のデ・ニーロの如く、実際に戦地へ舞い戻ってもよいし、あるいは、帰還先の日常に戦場を再現してしまってもよい。『夕凪の街』では、後遺の発症という形で、戦場への帰還が果たされる。
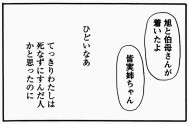
難病の時限爆弾な扱いも、この手の言説ではおなじみである。けれども、世界を眺める枠組みの変更が、ここでも情緒に新たな付加価値を与えている。
グレッグ・イーガン『宇宙消失』(2)
イーガンの不安な主題を端的に表現してしまえば、それは、選ばれたことの安堵とその裏返しとしての選ばれ得ないことへの恐怖、ということになるだろう。わたしどもが好んで挙げる例で説明すると、ある晩、刑務所に収監される夢を観た同僚のO氏は、枕を涙でずぶ濡れにして起床する始末となった。氏は、夢の中で、取り返しのつかない事態を至らしめた架空の罪科に悔恨していたのであり、それが起床後の実に見苦しき醜態を招いている。しかし、それはあくまで夢であって、覚醒を経れば平穏な市民生活が待ち構えている。したがって、氏の涕泣にはふたつの意味合いを仮託できるように思う。すなわち、空想の犯罪への後悔と、それが空想であったことへの安堵。イーガン風のモチーフに変換して語るのなら、罪の結果に苛まれる人格ではなく、平穏な会社員として生きる人格が、氏の生きる自分として選択されたことに氏は安堵し、そして、もし架空の罪科が架空でなかったらどんなことになっていたか、脅えるのである。
『順列都市』において、わたしどもはイーガンの不安をテクノロジーが可能にした自我の分岐に見ることができた。通常、体内の生理活動を基盤としている自我を、延命措置として、電子的な演算で表現する際に想定される心的なリスクというべきもので、その医学的措置が行われた後に目覚めた自分が、元の自分、つまり生化学的に自我を表現しているがゆえに、いつかは自我を失ってしまう自分であったらどうしよう、という選ばれ得ないことへの恐れである。
なお、延命措置としての思考の演算化は、例えばグレッグ・ベアでは、人格を外部メモリーにバックアップするという意味合いにおいて、そのアイデアが採用されている(『永劫』)。XPやMeのシステム復元を想起するとわかりやすい。オリジナルが事故等で生命活動を全うできなくなった際に、人格は復元ポイントの記憶まで退行して、復活することになり、イーガンの自我分岐による不安はここでは薄い。むしろ、復旧した自我の視点からすれば、数日か、数週間か、あるいは数年の空白が生まれてしまうことへの戸惑いがあるだろう(健忘する娘の外付けストレージ)。
ベアの語る人格のバックアップが、イーガンの不安を回避し得てるのは、やはり、自我の分岐が発生しないがゆえだろう。選出/選外をめぐる情緒が、けっきょくは、自我の分岐に基づいていることが、そこから理解される。では、『宇宙消失』はどのようにして自我の分岐を可能にして、その不安を語ってるのか? 観察問題へのファンタジーなアプローチがそこにやってくる。観察者の視角から外れる世界は、可能性の集積した混沌で、観察されるや否や、ひとつの現実へ収縮される。それが、今度は観察者自身に適用される。自分が自分を観察によって収縮できなくなった結果、自我は無数の可能上の自分へ分岐してしまう。
もっとも、『順列都市』に比べると、この分岐はファンタジー度が強すぎて、そのままでは心的な逼迫を実感させるには至らないように思う。今、ここで、わたしどもが存在していて、分岐の不安に脅えてるということ自体が、すでに可能性が収縮し、選出が終わってることと同義なので、割り切ってしまえないこともない。そこで、とにかくこの抽象的なる不安が具現するように、お話はキャラクターに無理難題な運試しを課して、いたずらに彼を一定のストレスにさらすことになる。