2003年12月の日記
『重罪と軽罪』のレビー教授は転がれる。かの映画の中でウディ・アレンは、劇中劇としてドキュメントフィルムを撮っていて、そこに登場するのが哲学者のレビー教授である。なんだか良くわからぬが取り敢えず萌え萌えな彼の言説が、わたしどもを悶えせしめる。
ウディ・アレンの作品では、劇中劇と劇の動的な関わりがたびたび描写される。不幸な主婦が映画と空想的(精神病理的)な交流をする『カイロの紫のバラ』とか、或いは小説家が自分の産んできたキャラに祝福される『地球は女で回っている』とか。いずれもファンタジーなお話である。ところが、『重罪と軽罪』における劇中劇としてのメタフィクションは記録映画であり、上記の作品のようにファンタジーな関わり合いをメインラインの物語へ敢行するには夢がなさ過ぎるかも知れぬ。この困難を逆手にとって、ファンタジー並の悶え感とドキュメンタリーな実存感を結びつけてしまうのが、レビー教授の萌え言説だったりする。
あくまで劇中劇の中にしか存在しないレビー教授は、物語の中途、自殺という形で持って舞台を退場してしまう。で、メタフィクションに存在しなくなった彼は何処へ行ったかというと、物語のラストシークエンスに語り手として登場したりする。此処に於いてレビー教授の劇中劇はウディ・アレンの住まう劇と等価なリアルで結ばれるように思う。
それでもって、レビーさんの東欧なまりなお言葉が、回想カットを絞めまくって物語を俯瞰し、調子に乗って回想カットの中に1カットだけ世界史なドキュメントフィルムまで入れてしまうものだから、物語はあざとく瞬時にして世界化して、ゴロゴロと転がざるをえない所と相成るのであった。
レビー教授のドキュメントは、物語の中ではあくまでノンフィクションという位置づけなので、メタフィクションを成す資格にそもそも欠けるかも知れぬ。とは云うものの、わたしども鑑賞者の座標系から眺めれば、フィクションにせよ、その中で演じられるノンフィクションにせよ、いずれもフィクションであったりするので、やっぱりメタな扱いをしても構わないのかも。
世界から退去したいと願っても、ただただ山奥で首をつるのでは芸がないと考えるのが人間の厄介な所で、アイデンティティや人生の定義付けを充足させるようなやりかたで生涯を任意に終わらせたがる美意識みたいなものがある。しかし、他者の美意識ほど迷惑なものも無いのであって、例えば北野武の『BROTHER』。死に場所探しにアメリカくんだりまでやって来て爆走の挙げ句、当人が蜂の巣になってしまうのはまだしも、ヘタレな真木蔵人やオマー・エプスを恐怖の余り泣かせるだけ泣かせて、わたしどもを大いに喜ばせたのであった。
『サムライ』のアラン・ドロンなんかも、死に場所探しと美意識が斯様に融合する顕著な類例だと思う。実弾に欠ける拳銃を人様に向けて故意に返り討ちを誘うお馴染みのアレである。
この様式は、人生に疲弊したおやぢが自殺をしたいが為にしばしば展開されるという意味合いに於いて、陰気で受動的な印象を受ける。ところが、80年代後半の香港では、シナリオライター時代のウォン・カーウァイが何を狂ったのか(或いはウー先生直後の無闇に熱い時代のなせる技だったのか)、「銃を向けてわざと返り討ち」様式をもっと積極的かつ肯定的に使えないかと思索した。そして産まれたのが、『マカオ極道ブルース』('87)の大転がりクライマックス。包囲する警官隊に自首せんとする巨悪を撃ちたいが、弾切れ。だったら己の身体を呼び水にして、警官隊に撃って貰えば良い――と云うことで、悽愴な結果がコレ…。


アラン・ドロンから思えば遠くへ来たものだと感に堪えないのであった。
静止画ではともかく、動画で観る『マカオ極道ブルース』の弾丸蜂の巣舞踊は、かなりメルヘンである。極端の様式美が、時として笑劇に成り果ててしまう見本のような感じと云うべきか。ただ、ここまでやっても『挽歌』以降に乱造された凡庸な英雄片の域を抜け出せないのが世の中の如何ともし難い所であったりする。足を洗ってせっかく築き上げたユンファの幸福家庭生活が駄目兄貴のとばっちりで崩壊してしまう模様は苛立たしさが先走り、どうにも鑑賞者の理解と感情の高揚感に欠けてしまう。
無駄に暑苦しい人生の破滅について80年代後半の香港人たちが斯様に七転八倒するのを傍目に、ブームの契機になった当のウー先生は『挽歌II』→『狼』と快調に地獄へまっしぐらで、行き着いた先があの崇高な怪作『ワイルド・ブリット』('90)だったりして、格の違いを見せて呉れる。たいへんにらぶらぶな時代であった。
『ワイルド・ブリット』の狂った素晴らしさは言を待たない。取り敢えず、冒頭で仲睦まじいトニー・レオン、ジャッキー・チュン、レイ・チーホンを見ただけで各々の末路を容易に予測できる配役のわかりやすさが過剰に素敵だ(これは前に触れたと思う――些か、後知恵の感も否めないのだが)。

と云う感じか。で、凶悪なラストカットがコレ…。
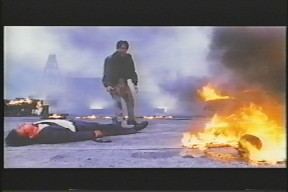
このカットはらぶらぶだ。とにかくわかりやすい。一目で見て、瞬時にナニしまくっている状況が理解できてしまう。同時に、映像媒体が如何に効率よく情報を伝えうるのか、わたしどもに教えてくれているようにも思う。恐らくテクストでは、ここまで効率よく情報を伝達するのは無理ではないか。
もっとも、その分だけ映像媒体にはテクストよりもコストがかかったりする。また、表現するものは同じであっても、それぞれの適正の違いから其処に至る道程に相違が産まれ、結果として棲み分けが行われたりするので、どちらが優れているかは一概には云えない。ただ、ヴィジュアルが即物的に先行してしまって、シナリオみたいな体を成すライトノベルなんかは、明らかに戦術を間違えているように思う。同じ土俵では映像媒体に敵うはずがないからである。
現役のとき受験に失敗して、泣く泣く予備校に通う羽目になった可哀想なわたしどもは、家に帰ると『英雄本色(日本語吹き替え版)』('86)を観て寝る→朝起きて予備校→帰宅して『英雄本色』→寝る→予備校→『英雄本色』以下略…な日々を繰り返して、知らぬ内に映像体験の歪んだ原風景を形成したのだった。Webサイトの名前もその英題にあやかって付けちゃったりして、ウー先生の御名前も不幸な予備校生だったわたしどもには神々しく轟いたのである(因みに大学に入って『エヴァ』に狂ったことは内緒だ)。
そんな偉大なる『英雄本色』。公開時の興行成績も偉大で、二匹目のドジョウを狙うべく類似品が多数乱造された。銃弾の蜂の巣になって踊り狂う景観が方々で展開され、わたしどもの暗い青春を慰めた。例えばこんな感じだ。
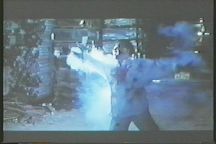





しかしながら、前に触れたように、その多くはウー先生の変態的な情熱の前に融解する他なく、物語を作ることの難しさについて、わたしどもに何事かを示唆して呉れるのみだった。いまにして思えば、極端な友情と云うホモセクシャルの描画にかけては、この地球上でウー先生に敵うものは存在し得ず、そこに半端なホモセクシャルをぶつけるのは間違いだったと云わねばなるまい。
『龍虎風雲』('87)の様な例外的な成功(結果として、それはミイラ取りになる潜入捜査と云う様式をグローバルに拡大することになった)はあったものの、一連の英雄片はウー先生の熱いホモセクシャルを前に閉塞を迎えつつあったと言って良い。それで、誰かが気づき始めたのですな、たぶん。ウー先生の同性愛には敵わないが、かれはヘテロセクシャルは苦手ではないかと。『人民英雄』('87)をそのように解釈しても良いのではないかと思う。アンチ英雄片を意識した作品だが、同時にウー先生にはとても描き得ない恋愛の物語でもあった。90年代に入って香港難病映画の最高峰『つきせぬ想い』('90)を撮っただけあって、イー・トンシンやりますなあと云う感じ。

もうひとり、あくまで異性間の恋愛を軸に英雄片を描こうと考えた人間がいて、それがウォン・カーウァイで『いますぐ抱きしめたい』('88)。ジャッキー・チュンのダメッぷりで気が狂いそうになりつつも、暫く会っていなかったいとこにアンディがらぶらぶでなんぢゃこりゃなお話に、わたしどもはウー先生の汗くさい呪縛から爽やかに離脱しようとする香港映画界の空気みたいなものを感じてしまう。同じくアンディらぶらぶな『天若有情』('90)もそんな印象だ。


これ以降、ウォン・カーウァイとウー先生の軌跡は対照的だと思う。『ワイルド・ブリット』で狂いまくって消尽したウー先生は、商業的普遍化の代償としてあの神々しい過剰を失ってしまう。一方でウォン・カーウァイは伝統的ジャンルとしての英雄片を再構築し、やがてジャンルすらも越えてしまった。これは、同じような時期に、伝統的やくざ映画を『3-4X10月』('90)や『ソナチネ』('93)でリニューアルした北野武と比較しても良い話ではないだろうか。
出勤する前に『みさき先輩ドラマCD』を聴いて、布団の中で悶転した。みさき先輩の言辞はいつも尤もらしく、気が狂いそうになる。
「わたし…あの時、夕焼けの屋上で浩平君と出会えなかったら、どうなってたんだろう?」
イヴェントの偶発的な一回性、希少性に対する感傷である。みさき先輩が、卒業と云う経験のもたらす情緒を、高校生活という日常の再帰不可能性と結びつけたことをわたしどもはまた前にも指摘した。経験の繰り返し得ないが故の切なさが、わたしどもを転がしてしまう。
ここでふと、テレビ版の『バトルアスリーテス大運動会』の終盤を思い出した。あかりは親友クリスの存在なしには今の自分があり得なかったことを語る(「クリスのおかげだよ〜」)。だが、自分の有無はあまり関係が無く、遅かれ早かれあかりは今のあかりになり得たとクリスは云う。
さらに話を変えて、昭和初期の日本。権威主義な空気の強まるその最中でさえ、内務官僚たちは、後十数年もすれば県令が民選で選ばれるようになることを半ば当たり前のこととして語り合っていたという。行政学の授業でそんなことを聴いて、妙に感心したことがある。詰まり、アメリカに勝とうが負けようが、時間の遅延はあるものの、結果はあまり変わらなかったのではないか。そんな空想も楽しい。
二年前の元旦にみさき先輩と出会わなかったら、わたしどもはどうなっていたのだろうか…。そんな問いかけには確かに感傷がある。しかし、二年前の元旦に先輩と出会わなかったとしても、遅かれ早かれどこかで出会っていたという考え方にもまた別の感傷がある。どちらをリアルに感じるかは、その人のこれまで送ってきた生活経験の在り方に左右されるのだろう。
斯様なことを考えている内に、ドラマCDはクライマックスに達した。もうナニがどうでも宜しくなったわたしどもは、会社に行く気を失ってしまった。
雁屋哲は、思弁が物理世界の在り方に介入するメルヘンをよく語る。例えば、『美味しんぼ』30巻に登場する土田康一。彼は富井副部長の親友の息子で、やせの大食いで、その性癖の為に幾度も恋人を失ってきた不幸な30代半ばである。
女性から嫌悪されるのにもうたくさんな土田が大食い癖を克服したいと願った所で、雁屋哲の精神世界が展開する。土田は山岡にハモ鍋を喰わされ、恍惚する(P21のあの顔はたぶん宇宙と交信しているのだろう)。それで、食べ物全般へ畏敬の念に目覚め、これまでの大食いが恥ずかしくなったりして、大食い癖は改まるのであった。
実際のところ、わたしどもはこの物語に薄気味悪い違和感を覚える。40合(推定)喰って「腹八分」と豪語する彼の大食いが、余りにも病理的なのだ。恐らく甲状腺か何かの病気ではないのだろうか。
気持ちの持ちようである程度は何とかなるような気もしないのではないが、あくまである程度であって、物理法則の壁がいつも人々の行動範囲を規定している。『美味しんぼ』でもその限界は認知されていて、大抵のトラブルは物理法則を越えない程度の解決手法で事足りるような範囲で発生する。だが、土田のような例外の物語もある。『美味しんぼ』の標準的な物理法則下においては、山岡はここで挫折せねばなるまい。ところが、雁屋は物理の世界を軽々と跳躍し、わたしどもを驚かせる。
思惟が物理法則を覆す物語を、わたしどもはファンタジーだとか内向的なサイエンスフィクションだとか、そんな名前で呼んでいる。『美味しんぼ』はそのいずれでもない。だから、ここでの居心地の悪さは、既定のジャンルからの逸脱に由来しているように思う(『アンブレイカブル』みたいなものか)。ただ、その逸脱ももっとあからさまだったら、例えば富井副部長の奇声が関東平野を灰燼せしめたりしたのなら、わたしどもはむしろ爽快を覚えたかも知れぬ。逸脱は微妙に何気なく行われたからこそ、居心地悪かったのではないか。
ゴジラの目の前でSSM-1を発射するのが取り敢えず悔しい。司令室フェティシズムが台無しである。なんかこう…、SSM連隊は奥多摩あたりにいて、そこの指揮統制装置がゴジラ近辺の捜索標定レーダとリンクする模様なんかを所望したい(『バトルオーバー北海道』みたく。こちらも参照)。それで巡航ミサイル風に地形に沿って飛んで行っちゃったりしたら失禁するのになあ。でも、地上を歩いているゴジラをアクティヴ・レーダーで識別して追尾とか出来るのか知らん? イメージでロックオンするASM-2なら何とかなりそうな感じだが[注]。
ひょっとしたらあのSSM-1、『ジパング』の異端なハープーンの如く、終末はレーザー誘導できるように改造されているのかも知れぬ。
[注]
となると、ニューヨークのゴジラに向かってホーネットが発射したハープーンって、IR誘導のE型なのか。
ある種のスケコマシ問題かも知れぬ。不幸な人間に恋慕する異常性癖への悩み。それは克服すべきものと認知されていて、その為に恋慕の対象となった人間を幸福にするということが、物語の動機になる。でも、彼が幸福になったら、いま彼より被っているドキドキ感は失われてしまう。そこに潜在的な切なさがある。
出勤前におでん二人前を喰って、気持ちが悪い。
大森荘蔵の『新知覚新論』を読む。以下、使えそうなネタの散文的な覚え書き。
過去と現在は存在の有り様の違いであって、どちらも現にここにあることには変わりがない。過去や思考、空想、想像は触れることはできない。しかし思い出すことはできる。
現実のおねいさんと会話ができるように、わたしどもは虚妄の中でみさき先輩とお話することはできる。ただ、生身のおねいさんと違って、わたしどもはみさき先輩に触れることができない。この触覚の可否が、「現実」と呼ばれるネットワークの歴史に参入できるか否かを決めている(←この言い方はらぶらぶ。覚えておこう)。触覚が存在の物理的な存続と密接な関わり合いを持っているからである。
「あいつらは女のやらかいパイオツをもみしだいてそれが手のひらの中でもうたまらんようにひしゃげるのを感じたことがあらへんのや」
現実回帰を求める文脈でよく使われるこのような言辞も、現実への参入契機としての触覚を語っている。もちろん、ここで優先されるのは現実である。他方、永野のりこの如く、価値が倒錯する可能性を言及しても良いだろう。すなわち「生身の女は気持ち悪い」(『土田君てアレですね!』)。
おもしろいのは、この倒錯がやがて「虚妄の中で非道いことをした分、生身のおねいさんには優しくなれよ」という言辞に作中で転換される所。やっぱり現実回帰、ともとれる。だが別の見方もできないか。
『すげこまくん』のらぶらぶな11巻、えむ子(ここでの文脈での虚妄)はヨシオお兄さんへ現実への回帰を訴える。が、同時に虚妄である自身がヨシオお兄さんを支え得たことに、自身の価値を見出そうとする。けっきょく虚妄も現実も、わたしどもには直に現れる。ただ、在り方が異なるだけなのだ。
で、以下、脈絡が無くなるのであるが。
正直、死ぬのは恐ろしい。だから、身体への危険を意識するネットワークの歴史が優先されるのは自然である。しかし自我の消失への恐怖が、エコロジー風の機能主義で説明された時、わたしどもは例えば「人殺し」を倫理的に否定する術を失い、それに伴って現実への優先付けを感情以外で説明できなくなってしまう気がする。
この機能主義を乗り越えるには、そもそもの問題を最初からから無くすか、すり替えてしまえばよいかも知れぬ(議論が雑かも)。つまり、自我が失われなければ、何も怖がる必要はない。身体が失われたとしても自我の継続を保証する宗教的な問題になる。もっとも、何も怖くないのなら「人殺し」も怖くない事になりかねないが、これも宗教の範疇であって、現実の「倫理」に沿った生き方が自我の継続性を保証するという強迫がある。しかし、信仰のない人間にとってこの論説は納得に欠ける。
えむ子とヨシオお兄さんの結末は、ある意味で示唆的である。えむ子を失っても、ヨシオお兄さんはまんがを描き続ける。書店で彼の作品を発見したえむ子は、自分の存在が無駄でなかったことを知る。
わたしどもは誰かの想い出になりたいと願う。だが、他者の想い出の中でわたしどものイメージが継承されたとしても、自我が継承される訳ではない。これは前に指摘した。その一方で、わたしどもは自我の断片が世界に拡散して行く様に何となく感動する。
ヨシオお兄さんの物語は、彼の死後も彼の存在を証明し続けるだろう。残されたその物語は、当人の手から離れているが故に、想い出であり虚妄であっていわゆる現実ではない。ただ、ヨシオお兄さんは、自分が居なくなった将来、自我の継続はとうてい望むべくもないが間接的に自己の存在を保証してくれるかも知れぬその虚妄のために、今この現実へ関与せねばならない。
この考え方は現世の在り方が来世を規定するという宗教的な世界観と似てなくもない。
マンガと実写の情報量の違いに戸惑いが感ぜられる。実写が豊穣な情報量を誇るのも善し悪しがある。制御を怠ると見たくないものまで見えてしまう。阪本順治のレイアウトは美しいものの、抽象的な原作の背景に比べると映画のそれは小汚くてイヤイヤである。
以下、ちょっと話が飛ぶ。
誰しも美しいものだけ見ていたい。しかし一方で、汚いものから目を背けることをわたしどもの属する共同体は倫理的に宜しくない行為であると見なしがちだ。もっとも問題はもっと根元的かつ深刻で、美しいものだけを見ていたいのではなくて、もはや美しいものしか見えないのかも知れぬ。取り敢えず消失点に消えて行く電柱やブロック塀が美しい。パースが狂わないこの世界が美しい。主観を通した世界は何を見ても泣けてくる。ところが、主観というフィルターが薄れた時、世界は途方もなく汚れてくる。
例えば、他人が資料用にデジカムで撮った世界。下手な演出意図など全くないため、神々しいほど世界が汚い。水が汚い。空が汚い。壁が汚い。床が汚い。人が美しくない。
競艇場を取材した斯様なビデオを観る同僚O氏の足も汚かった。あまりの酷さに、撮影監督のN氏が氏の足に消臭剤を吹き付けたが、悪臭が余計に立ちこめるだけだった。
芥川の『河童』をご飯食べながら読んだ。「メイド萌えは無意識的に悪遺伝子を撲滅しようとする行為である」な件で噴飯する。